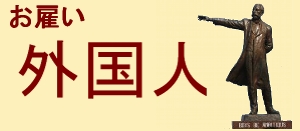お雇い外国人・開国後に来日した外交官、役人、技術者、宣教師、学者の他、芸術家、商人、ジャーナリストらを特集。
長い鎖国時代が終わり、明治政府が成立すると、政府は積極的にアメリカ、ヨーロッパ諸国に働きかけて様々な分野の専門家を日本に招き、彼らの教えを受けて「近代化」を図った。当時の日本人にとっての近代化とは=西洋化のことであった。結果、1898年くらいまでの間にイギリスから6,177人、アメリカから2,764人、ドイツから913人、フランスから619人、イタリアから45人の先生や技術者が来日したとされる。彼らは「お雇い外国人」などと呼ばれ、本格的な開拓が必要だった北海道はもちろん、日本全国に渡って献身的に日本に尽くし、政治・経済・産業・文化・教育・芸術など多くの分野や日本人の精神に大きな影響を与えた。
主にイギリスからは鉄道開発、電信、公共土木事業、建築、海軍制を、アメリカからは外交、学校制度、近代農事事業・牧畜、北海道開拓などを、ドイツからは医学、大学設立、法律など、フランスからは陸軍制、法律を、イタリアからは絵画や彫刻といった芸術を学んだ。
また、この時期、東京・横浜・神戸などに設立された大使館に派遣された公使・大使・領事ら役人や、貿易のため自ら来日した商人、日本を海外に紹介するため取材に訪れたジャーナリスト、江戸時代のキリスト教禁止令の破棄を受けて布教に来た外国人なども少なくない。
参考資料
井上琢智著
『黎明期日本の経済思想―イギリス留学生・お雇い外国人・経済学の制度化 (関西学院大学経済学研究叢書) 』 』
荒俣宏著
『開化異国(おつくに)助っ人奮戦記 (小学館ライブラリー) 』 』
プランニングコーツ編
『外国人が残した日本への功績 』 』
片野勧著
『明治お雇い外国人とその弟子たち 』
』 |
|
|
|
| 名 | (生年~没年)解説 | おススメ資料 |
リチャード・ヘンリー・ブラントン
Richard Henry Brunton | (1841~1901)
イギリス・スコットランド出身の工兵技監にして建築家。1868年明治政府から英国政府に要請され招かれたお雇い外国人の第1号。和歌山県串本町の樫野崎灯台をはじめ数多くの灯台設置を手がけ、勤務していた約8年間に灯台26台を設計した。このため「日本の灯台の父」と讃えられている。また日本初の電信架設の他、道路舗装・公園設計・鉄道建設・築港などにも尽力した。まず彼のような灯台技師が来たのは、早急に外国の船を安全に日本の港に誘導する必要があったからである。
| 『お雇い外人の見た近代日本 (講談社学術文庫) 』 』 |
ボアソナード
Gustave Emil Boissonade | (1825~1910)
パリ大学卒のフランスの法学者。グルノーブル大学、パリ大の助教授などを経て明治政府の招きで1873年来日。刑法・治罪法・民法を草案した。このうち民法は日本の風俗習慣に適さずとして反対され施行はされなかった。司法省法律学校、東京大学で教鞭をとり、西欧法学の移入に尽くした。
| 『ボアソナード論文撰 』 』 |
ロエスレル
Karl Friedrich Hermann Roesler | (1834~1894)
ドイツの法学者。明治初期伊藤博文らの招きで来日し明治憲法・商法など諸法令の起草をした。
| 『ロェスレル氏起稿 商法草案 』 』 |
アルベルト・モッセ
Albert Mosse | (1846~1925)
ドイツの法学者。ロエスレルとともに来日し憲法・諸法令の起草をした。
| 『大日本憲法講義 (近代日本憲法学叢書 (別巻1)) 』 』 |
ルートヴィッヒ・リース
Ludwig Riess | (1861~1928)
ドイツの歴史学者。東京大学史学科を創設し実証主義歴史学を広めた。
| 『ドイツ歴史学者の天皇国家観 』 』 |
ルイ=エミール・ベルタン
Louis-Emile Bertin | (1840~1924)
フランスの海軍技術者。日本海軍に招かれ、1886年から1890年の4年間来日して日本人技術者と船舶設計技師を育て上げ、近代的な軍艦を設計、建造し、海軍の施設・呉、佐世保工廠などを建造・指揮した。この間に彼が手がけたのは実に海防艦「松島」「橋立」「厳島」(通称「三景艦」)をはじめとする7隻の主力艦と22隻の水雷艇に及び、これらは日清戦争における日本艦隊の主力となった。帰国後は海軍機関学校校長、造機大将、海軍艦政本部部長を歴任、在任中にフランス海軍を世界2位の海軍に育て上げた。その功績を記念してフランス海軍にはエミール・ベルタンの名を冠した巡洋艦があった。 | 
|
ジョサイア・コンドル(コンデル)
Josiah Conder | (1852~1910)
イギリスの建築家。1877年来日、工部大学校(現・東京大学工学部)の教授となり、日本人建築家辰野金吾らを育てた。東京・丸の内のレンガ街、鹿鳴館、ニコライ堂、古河虎之助邸(現・旧古河庭園大谷美術館)などを設計した。日本の絵画、生け花、日本庭園についての著作もあり、海外への紹介に尽くした。日本人と結婚し東京で死去した。
参考書は→ 国際結婚のコーナーで。 国際結婚のコーナーで。 | 『河鍋暁斎 』 』
『美しい日本のいけばな 』 』
畠山けんじ著
『鹿鳴館を創った男―お雇い建築家ジョサイア・コンドルの生涯 』 』
永野芳宣著
『物語 ジョサイア・コンドル―丸の内赤レンガ街をつくった男 』 』 |
グイド・フルベッキ
Guido Herman Fridolin Verbeck | (1830~1898)
オランダ人宣教師。母国で工学を学んだ後、アメリカに移住。1859年来日し、幕府が長崎につくった英語伝習所(済美館)の英語講師となり、維新後は上京し東大の前身である開成学校の講師(初代教頭)、南校の教頭、そして明治学院で講師・理事を務めた。南校時代の月給は太政大臣の三条実美が800円、参議が500円の時代に600円という高給だった。坂本龍馬、西郷隆盛、高杉晋作、岩倉具視、大久保利通、伊藤博文、勝海舟、桂小五郎など幕末の主な志士たちを集めて撮ったといわれる謎の「フルベッキ写真」でも有名。
| 『フルベッキ書簡集 (1978年) 』 』
大橋昭夫、平野日出雄著
『明治維新とあるお雇い外国人―フルベッキの生涯 』 』
加治将一著
『幕末 維新の暗号 』 』 |
ウィリアム・グリフィス
William Griffis | (1843~1928)
米・フィラデルフィア生まれ。フルベッキとその門下生で留学生だった福井藩士・日下部太郎の紹介で1970年来日、まず福井藩の教育に当たり明新館で教鞭をとる。その後政府に雇われて1972年、南校(後の東大)に移り、理学や化学を教え、同時に日本人向けの英語の教科書作りを目指し、現在でも使われているような身近な生活に題材を取った挿絵入りの教科書を作った。1875年に帰国。帰国後は日本の紹介に務め、講演や執筆活動を行った。1876年にアメリカで刊行した『The Mikado's Empire』( 『ミカドの帝国』、『皇国』または『ミカド』)は日本と明治天皇を紹介する書籍として広く読まれた。
| 『ミカド―日本の内なる力 (岩波文庫) 』 』
『アメリカ古典文庫 22 アメリカ人の日本論 』 』 |
ヘボン(ヘプバーン 平文)
James Curtis Hepburn | (1815~1911)
アメリカ人宣教師。14歳でプリンストン大に入学した秀才で、ペンシルバニア大医学部卒の医師でもある。ペリーの報告書を読んで日本に興味を持ち、妻クララとともに1859年来日。医療活動の他、宣教のため日本語習得を研究を重ね、美国平文の名で1867年英和辞典『和英語林集成』を発行、聖書の和訳などにも貢献、またヘボン式ローマ字を考案した。1863年(文久3年)横浜にクララとともにヘボン塾を開設、後に明治学院大学を設立、初代学長になり、化学・衛生学などを教え日本人の教育に務める。門下からは島崎藤村、高橋是清など逸材を輩出した。33年に渡り日本で活動したのち帰国した。
当時の日本語表記は「ヘボン」だが英語のスペルはオードリー・ヘップバーンやキャサリン・ヘップバーンと同じHepburnである。 | 『和英語林集成 (講談社学術文庫 477) 』 』
内藤誠著
『ヘボン博士のカクテル・パーティー 』 』
杉田幸子著
『ヘボン博士の愛した日本 』 』
村上文昭著
『ヘボン物語―明治文化の中のヘボン像 』 』
ウイリアム・エリオット・グリフィス著
『ヘボン―同時代人の見た 』 』 |
ニコライ・カサートキン(聖ニコライ)
Nikolai(Ioan Dimitrovich Kasatkin) | (1836~1912)
ロシア正教の宣教師。ニコライは修道士名。1861年に来日、函館ロシア領事館附属礼拝堂司祭として着任。日本ハリストス正教会を創建後、上京し神田駿河台に本部となる通称ニコライ堂を建て布教を行った。日露戦争中も日本に滞在し日露の友好に努めた。関東大震災で消失したと思われていた日記が近年になって発見され2007年に日本語版が出版された。
| 『宣教師ニコライの日記抄 』 』
中村健之介著
『宣教師ニコライと明治日本 (岩波新書) 』 』 |
L.L.ジェーンズ
Leroy Lansing Janes | (1838~1909)
アメリカの宣教師・教育家。名門ウエスト・ポイント陸軍士官学校を卒業し、1871年来日、開校されたばかりの熊本洋学校で教鞭を取り、文学、算術、地理、化学、測量、作文、演説などをすべて一人で英語で授業を行った。男女共学、キリスト教に基づく博愛主義などは向学心に燃える若者たちに大きな影響を与え、徳富蘇峰ら多くの優秀な人材を育てた。熊本にはジェーンズが住んだ洋学校教師館がジェーンズ邸として残されている。ここは後に博愛社=日本赤十字の発祥の地となった。
| フレッド・G. ノートヘルファー著
『アメリカのサムライ―L.L.ジェーンズ大尉と日本 (叢書・ウニベルシタス) 』 』 |
ラファエル・フォン・ケーベル
Raphael von Koeber | (1848~1923)
ドイツ系ロシア人の哲学者。モスクワ音楽院ピアノ科ではルビンシュタインやチャイコフスキーに師事していたという異色の経歴を持つ。ドイツに留学してハイデルベルク大学などで哲学を学ぶ。井上哲次郎らの要請で1893年来日し東京大学でギリシア哲学、美学、美術史などを講義、夏目漱石、高山樗牛、岩波茂雄、阿部次郎、西田幾多郎らも聴講した。また東京音楽学校(現・東京芸大)の講師も務め滝廉太郎などを育てた。第一次世界大戦が勃発して帰国できなくなり、横浜のロシア総領事ヴィルム邸で晩年を過ごし、論文や歌曲を残した。夏目漱石や和辻哲郎は『ケーベル先生』という一文を残している。
| 『ケーベル博士随筆集 (岩波文庫) 』 』 |
フェノロサ
Ernest Francisco Fenollosa | (1853~1908)
アメリカの美術史学者、哲学者。ハーバード大卒。1878年来日し東大文学部で政治学、理財学、哲学などを講義し日本の思想史に大きな影響を与えた。また日本美術の研究に努め、弟子岡倉天心らとともに東京美術学校(現東京芸大)の創設に尽くした。日本の古美術や浮世絵の認識・紹介に力を注ぎ日本美術界に大きな足跡を残した。1890年に帰国したがボストン美術館の東洋美術部長となって日本美術の紹介に貢献した。日本の仏像や陶器、絵画、建築に「美術」の概念を与えた功労者である。
| 村形明子著
『アーネスト・F・フェノロサ文書集成―翻刻・翻訳と研究 』 』
保坂清著
『フェノロサ―「日本美術の恩人」の影の部分 』 』
山口静一編・著
『フェノロサ社会論集 』 』 |
ヴィンチェンツォ・ラグーザ
Vincenzo Ragusa | (1841~1927)
イタリアの彫刻家。1872年、ミラノの全イタリア美術展でウンベルト殿下賞という最高賞を受賞し名を知られた。1876年来日し工部美術学校で西洋式彫刻技法を教えた。妻は画家のお玉(清原多代・ラグーザお玉)で、1882年ラグーザはお玉を連れて故郷シチリア島パレルモに帰った。
明治時代の著名人の彫刻を多く手がけ、『伊藤博文像』などが残されている。 | 木村毅著
『ラグーザお玉自叙伝 』 』
参考書は↓ 国際結婚のコーナーで。 国際結婚のコーナーで。 |
フォンタネージ
Antonio Fontanesi | (1818~1882)
イタリアの画家。ラグーザと共に日本の本格的な近代美術の基礎を築いた人物。1848年イタリアの市民革命に投じてガリバルジ軍に参加したが失脚後はジュネーブに逃れる。パリやフィレンツェで美術を学び、トリノの王立アルベルティナ美術学校で風景画教師を務める。1976年、創設された工部美術学校に招かれ洋画を教えた。わずか2年あまりの滞日だったが後の日本美術界へ大きな影響を残した。門下生に浅井忠、五姓田義松、小山正太郎、松岡寿、山本芳翠などがいる。 | 松井貴子著
『写生の変容―フォンタネージから子規、そして直哉へ 』 』 |
エドアルド・キヨソネ
(キヨッソーネ)
Edoardo Chiossone | (1831~1891)
イタリア出身の銅板画家・印刷技術者。1875年来日、大蔵省印刷局にて銀行券や印紙のデザインや原版作りを行い、銅版技術を指導した。この時技術を学んだ木村延吉、降矢銀次郎は後に大手の印刷会社・凸版印刷を興した。西郷隆盛・明治天皇・大久保利通など著名人の肖像画を多く描いている。日本で初めて紙幣の肖像画に描かれた神功皇后像(どう見ても日本人に見えないが)も彼の手による。退職後は、鎌倉に残り、日本の風景、寺社、古器物、古美術を本国イタリアに紹介。これらの遺品や作品は故郷ジェノバのキヨソネ博物館に保存されている。 | 明治美術学会、印刷局朝陽会編
『お雇い外国人 キヨッソーネ研究 』 』 |

ラフカディオ・ハーン(ヘルン)
(小泉八雲)
Patrick Lafcadio Hearn | (1850~1904)
モラエス、フェノロサと並ぶ日本紹介者で、この時代に来日した外国人の中でも最もよく知られた人物。父はアイルランド人、母はギリシア人。ギリシャのレフカダで生まれ、アイルランド、フランス、ロンドンで学び、アメリカの新聞社に勤務するなど根っからの「国際人」であった。1890年、ローウェルの『極東の魂』を読んで日本に興味を持ったハーンはまず新聞記者として来日。すぐに日本に魅せられ改めて島根県松江尋常中学校に英語教師として赴任。その後松江の士族の娘小泉節子と結婚、熊本の第五高等学校に転勤した。すっかり日本の虜となり、日本に馴染んだハーンは1896年帰化し、妻の旧姓から「小泉」、日本最古と言われる和歌「八雲立つ出雲八重垣妻ごみに、八重垣つくるその八重垣を」に現れる、「出雲国」にかかる枕詞の「八雲立つ」に因んで「八雲」と名乗った。同年から上京して東京帝国大学や早稲田大学で英文学を講じながら、『日本瞥見記』『東の国から』などの随筆を書き、様々な視点から日本の姿を欧米諸国に紹介した。その中でも1904年アメリカで刊行された『怪談』は、日本の古典や民話などに取材した創作短編集であり、その中の『耳無し芳一』『雪女』『貉』などは日本人にもよく知られ愛された物語となっている。松江に残された居住跡は1940年に国の史跡に指定されている。妻の回想『思ひ出の記』にハーンの好きなもの嫌いなものリストがあり、彼の人物像が良く見えて面白い。好きなもの=西、夕焼、夏、海、遊泳、芭蕉、杉、淋しい墓地、虫、怪談、浦島、蓬莱、マルティニークと松江、美保関、日御碕、焼津、ビフテキ、プラム・プディング、煙草。嫌いなもの=うそつき、弱いもの苛め、フロックコートやワイシャツ、ニューヨーク。「日本人は最も少ない費用をもって最も多い楽しみを味わう人種である」彼の残した言葉だが、日本人は精神的な楽しみを重んじる天才と謳っている。今の物質に依存した娯楽にあふれた日本を見たら彼は何て言うだろうか?
愛妻との馴れ初めなど、参考書は→ 国際結婚のコーナーで。 国際結婚のコーナーで。 |
『明治日本の面影 (講談社学術文庫―小泉八雲名作選集) 』 』
太田雄三著
『ラフカディオ・ハーン―虚像と実像 (岩波新書) 』 』
小林正樹監督の名作
『怪談 』 』
小泉節子著
『思ひ出の記 』 』
藤森きぬえ著
『ヘルンとセツの玉手箱―小泉八雲とその妻の物語 』 』 |
ホーレス・ケプロン(またはホリス・ケプロン)
Horace Capron | (1804~1885)
アメリカの北海道の開発顧問。1871年来日。当時67歳で現職のアメリカの農務長官という大物だったが、明治政府が黒田清隆開拓使次官をアメリカに派遣、大臣並みの高給で依頼し招いたといわれる。アメリカでは西部開拓の第一人者としてカリフォルニアにグレープフルーツやオレンジ等を広めた人物で、日本にも紅玉などのりんご等多くの果物をもたらした。アメリカ式の近代農業を広め、酪農やビール醸造(後のサッポロビール)、鉱業や水産業、道路整備の指導にも当り、1875年帰国するまで北海道のみならず日本の産業界に大きな足跡を残している。札幌農学校の講師としてクラーク博士を推薦し招聘した人物としても知られる。
| 富士田金輔著
『ケプロンの教えと現術生徒―北海道農業の近代化をめざして 』 』 |
デビッド・モルレー(マーリまたはマレー)
David Murray | (1830~1905)
アメリカの教育行政の専門家。森有礼の推薦で1873年に来日し文部省学監となり、小学校他新しい学校制度、教育制度を設置するのに尽力した。1878年帰国。
| (調査中) |
デュ・ブスケ(ジュ・ブスケ)
Albert Charles Du Bousquet | (1837~1881)
フランスの軍人。1867年フランス軍事顧問団の一員として来日し、幕府歩兵に調練を実施した。戊辰戦争後もフランス公使館通弁官として日本に残り、官営・富岡製糸場の建設などに力を尽くした。1881年45歳で死去。青山霊園の墓碑には「治部輔」と刻まれている。
| (調査中) |
ジョルジョ・ブスケ
Georges Hilaire Bousquet | (1843~?)
フランスの法学者。パリ控訴院弁護士だったが、1872年明治政府の顧問となり司法省法学校などで法律などの指導に当たった。司法卿江藤新平の要請で刑法・司法制・警察制度などの構築に貢献した。彼が日本国内で触れ・経験した文化や風俗などは日記に纏められて出版され当時の貴重な資料となっている。
| 『日本見聞記―フランス人の見た明治初年の日本 1 』 』 |
ポール・ブリューナ
Paul Brunat | (1840~1908)
フランス人。1869年来日し横浜のフランス貿易会社の生糸検査人をしていたがブスケの推薦を受け1871年に明治政府に雇われ、器械製糸による製糸場の建設と繰糸技術の指導を任された。設立場所を求めて日本各地に調査をしたが、もともと養蚕業が盛んで東京・横浜に近い群馬・富岡に日本初の器械製糸工場を設立した。母国フランスから建築家バスチャンはじめ技師らを招き、繰糸機や蒸気機関等を輸入して1972年に操業を開始、この官営富岡製糸工場は日本の殖産興業に大きな貢献をした。 | 富岡製糸場世界遺産伝道師協会編
『世界へはばたけ!富岡製糸場―まゆみとココのふしぎな旅 』 』 |
エラスムス・ペシャイン・スミス
E. Peshine Smith | (1814~1882)
アメリカ人。リンカーン大統領の経済顧問だった。外務省・明治天皇の顧問として招かれ、1871年から1877年まで滞在し新しい外交技術や法律を教えた。また、日朝間の調整など外交にも尽力した。 | (調査中) |
| セルギー(セルギイ)・チホーミロフ | (1867~1944)
ロシア出身のハリストス正教会の府主教。1908年来日、ニコライの後を継いだが太平洋戦争中はソ連のスパイの疑惑がかけられ特高に捕らえられ拷問を受け、それがもとで亡くなった。 | (調査中) |
| セルギー(セルギイ)・ストラゴロツキー | (1867~1944)
ロシア出身のキリスト教伝道者。サンクト・ペテルブルグ神学大学卒業。ハリストス正教会掌院、ロシア革命後初の総主教などを務める。1890年来日、日本でのロシア正教布教に努めた。1898年に北海道を旅し『蝦夷旅行記』を記した。帰国後にモスクワ総主教となった。 | 『ロシア人宣教師の「蝦夷旅行記」 』 』 |
メアリー・P.プライン
Mary P.Pruyn | (1820~1885)
1872年から1875年の間、宣教師として日本の横浜に滞在したアメリカ人女性。教師としてアメリカン・ミッション・ホーム(現在の横浜共立学園)を設立するなど女子教育に心血を注いだ。故国の3人の孫に宛てて書いた手紙集「グランドママの手紙」が翻訳されて出版されている。 | <『ヨコハマの女性宣教師―メアリー・P.プラインと「グランドママの手紙」 』 』 |
メアリー・E・キダー
Mary.E.Kidder | (1834~1910)
アメリカの女性教育者。1869年、35歳で来日し、ヘボンの門下でクララ夫人のヘボン塾で英語を教えた。その後本格的な女子教育の活動に従事し横浜・山手に学校(後のフェリス女学院)を創設した。 | 山野辺由美著
『キダーさんの学校―フェリス女学院創立までのあゆみ 』 』 |
A.B.ミットフォード(リーズデイル卿)
Algernon Freeman-Mitford, 1st Baron Redesdale | (1837~1916)
イギリスの外交官・著述家。英国公使館書記官として1866~70年の間日本に滞在し、幕府および明治維新後の新政府との外交交渉に尽力した。本書のほかに『昔の日本の物語』『英国外交官の見た幕末維新―リーズデイル卿回想録 (講談社学術文庫) 』など、日本に関する著作がある。 』など、日本に関する著作がある。 | |
| ハルブ神父 | (1864~1943)
1889年に来日し、長崎、大分、奄美大島などで布教活動を行い、天草に崎津教会を建てたフランス人神父。幼稚園の設置など子供たちの教育にも尽くした。 | 広瀬敦子著
『よみがえる明治の宣教師 ハルブ神父の生涯 』 』 |
ジョルジュ・ビゴー
Georges Ferdinand Bigot | (1860~1927)
フランスの画家・漫画家。パリの名門エコール・デ・ボザールを退学し、挿絵画家となる。1882年来日、陸軍士官学校で講師をしながら、当時の日本の出来事を版画・スケッチなどの形で風刺画にあらわした。在日フランス人のための風刺漫画雑誌『トバエ』を創刊、日本を題材にした風刺漫画を多く発表した。ユニオシのような「出っ歯・メガネの日本人像」の創始者といえる。 | 『ビゴー日本素描集 (岩波文庫) 』 』
清水勲編・著
『ビゴーが見た明治ニッポン (講談社学術文庫) 』 』 |
フランツ・フェルディナント
Franz Ferdinand Karl Ludwig Josef von Habsburg-Lothringen, Erzherzog von Osterreich-Este | (1863~1914)
ハプスブルク(オーストリア=ハンガリー)帝国の皇位継承者。1893(明治26)年、世界一周の旅の一環としてオーストリア海軍の軍艦・エリザベート皇后号に乗って長崎に来日。一行はこれより約3週間の行程で長崎-熊本-下関-宮島-京都-大阪-奈良-大津-岐阜-名古屋-箱根-東京-日光と巡り、その時の様子は克明に日記に残されている。オーストリアの宮殿には日本庭園がある。サラエボで暗殺されこれが第一次世界大戦勃発のきっかけになった。因みに彼の名を取ったイギリスのロックバンド がある。 がある。 | オーストリア皇太子の日本日記―明治二十六年夏の記録 (講談社学術文庫) |
エリザ・R. シドモア
Eliza Ruhamah Scidmore | (1856~1925)
『ナショナルジオグラフィック』の紀行作家であり地理学者。女性として初めて米国地理学協会の理事に就任し、東洋研究の第一人者として活躍した。世界中を旅したが、兄が駐日領事館副領事だったことで1884年に来日以来、日本には3度も訪れて合計3年間滞在し全国を行脚して様々な記録を残した。隅田川に沿う向島の桜に心惹かれ、後にタフト大統領夫人に進言してワシントン・ポトマック河畔の桜植樹に尽力した。スイスで死去したが、墓は横浜外人墓地にある。 | 『シドモア日本紀行―明治の人力車ツアー (講談社学術文庫) 』 』
『日露戦争下の日本―ハーグ条約の命ずるままに ロシア軍人捕虜の妻の日記 』 』 |
ハインリッヒ・シュリーマン
Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann | (1822~1890)
ドイツの考古学者。事業に成功し実業家として活躍した。40歳過ぎてから考古学に本格的に取り組み、ギリシア神話に出てくるトロイの都市を発掘し実在することを証明した。1864年世界漫遊に旅立ち、幕末に日本を訪れ、約3ヶ月に渡って江戸を中心に旅を続け、日本を絶賛する詳細な記録を残している。 | 『シュリーマン旅行記清国・日本 (講談社学術文庫 (1325)) 』 』 |
エメェ・アンベール
Aime Humbert | (1819~1890)
1863年に日瑞修好通商条約締結のため来日したスイスの時計業組合会長。後に国会議員。長崎・京都・鎌倉などを旅行し、庶民や武士の生活・美術工芸品など詳細を多数スケッチで残した。 | 『絵で見る幕末日本 (講談社学術文庫) 』 』 |
エドゥアルド・スエンソン
Edouard Suenson | (1842~1921)
デンマーク生まれのフランス海軍士官、デンマーク海軍大臣副官を経て大北電信会社社長。フランス公使ロッシュ付添武官として王政復古直前に来日した。ロッシュの近辺で見聞した貴重な体験を日記に綴った。将軍慶喜との謁見の模様やその舞台裏、横浜の大火、テロに対する緊迫した町の様子、また、日本人の風呂好き・日本女性の接客など悪習や弱点までも指摘している。
| 『江戸幕末滞在記―若き海軍士官の見た日本 (講談社学術文庫) 』 』 |
アドルフ・フィッシャー
Adolf Fischer | (1856~1914)
オーストリアの東アジア美術史家、東アジア民族研究家。ケルン市東洋美術館館長。1892年に初来日、日本に魅了され生涯に7回も来日した。明治期の日本人の気質や日本の自然・風景を絶賛した『明治日本印象記』を残している。ドイツ人女性美術史家フリーダと結婚し新婚旅行も日本であった。フリーダにも日本美術についての著作がある。 | 『明治日本印象記―オーストリア人の見た百年前の日本 (講談社学術文庫) 』 』
フリーダ・フィッシャー著
『明治日本美術紀行―ドイツ人女性美術史家の日記 (講談社学術文庫) 』 』 |
エセル・ハワード
Ethel Howard | (1865~1931)
ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世の皇太子、シャム国王の甥などを教育した英国婦人。1901(明治34)年日本に招かれ、約7年に渡って元薩摩藩主島津家の忠重ら5人の子息の教育を託された。そのときの日記が残されており、そこには当時の上流社会の家庭の様子と日本の風俗や日本人の気質が綴られている。 | 『明治日本見聞録―英国家庭教師婦人の回想 (講談社学術文庫) 』 』 |
ロバート・フォーチュン
Robert Fortune | (1812~1880)
英国スコットランド生まれ。エディンバラ王立植物園の園丁を経てロンドン園芸協会へ。後、英国東インド会社の依頼で中国からインドに茶の木を移植して有名になる。キク、ラン、ユリなど東洋の代表的観賞植物も英国に紹介。1860年と61年訪日。長崎、江戸などを歴訪。稲や養蚕、金柑などの多くの栽培を研究・記録を残し、また団子坂や染井村の植木市など各地で珍しい園芸植物を手に入れるだけでなく、茶店や農家の庭先、宿泊先の寺院で庶民の暮らしぶりを自ら体験。日本の文化や社会を暖かな目で観察する一方、桜田門外の変、英国公使館襲撃事件や生麦事件など生々しい見聞も残した。キンカン属の学名Fortunellaは、彼に献名されている。 | 『幕末日本探訪記―江戸と北京 (講談社学術文庫) 』 』 |
ジョン・レディー・ブラック
John Reddie Black | (1827~1880)
幕末に来日、横浜で「ジャパン・ヘラルド」をはじめ新聞事業を次々に手がけたイギリス人記者。横浜と江戸を中心に、近代化への夜明けを迎えた日本の状況や風俗などを記録した。息子は落語家初代快楽亭ブラック。
| 『ヤング・ジャパン―横浜と江戸 (1) (ワイド版東洋文庫 (156)) 』 』 |
アルフレッド・ルサン
Alfred Roussin | (1839~1919)
フランスの海軍士官。幕末の日本を訪れ、英米仏蘭の連合艦隊による下関砲撃(下関戦争または馬関戦争)に従軍し、詳細な記録を残している。 | 『フランス士官の下関海戦記 』 』 |
ヴィットリオ.F.アルミニヨン
Vittorio F. Arminjon | (1830~1897)
サヴォイア(現フランス領)生まれ。イタリアの軍人、外交官として活躍。文人として数冊の著書や論文も残した。良質の蚕卵紙購入が動機で、マジェンタ号艦長として通商を求め来日した。 | 『イタリア使節の幕末見聞記 (講談社学術文庫) 』 』 |
ウィリアム・ホィーラー
William Wheeler | (1851~1933)
札幌農学校の第2代教頭。土木工学を専門とし多くの優秀な門下生を育てた。札幌の時計台の基本設計を行った人物として知られている。 | 高崎哲郎著
『評伝・お雇いアメリカ人青年教師ウィリアム・ホィーラー 』 』 |
エドウィン・ダン
Edwin Dun | (1848~1931)
アメリカの牧畜家。マイアミ大卒後、父や叔父の牧場で獣医学、競走馬・肉牛の研究をしていた。ケプロンの推薦を受け1873年北海道開拓の技術者として来日。函館に赴任して近代農畜産の技術指導に当たる。後に札幌に移り複数の牧場建設に当り、牛・豚・羊などの飼育から乳製品の製造まで教える。また、競馬場の提案もして日本初の西洋式競馬を開設した。開拓使が廃止されて一時帰国するが、日本での実績が評価されて1884年、アメリカ公使館二等書記官として再来日。後に公使まで出世した。日本人と結婚し、日本に永住を決意、公使退官後は日本の民間企業に勤め、東京の自宅で死去した。 | 赤木駿介著
『日本競馬を創った男―エドウィン・ダンの生涯 (集英社文庫) 』 』
田辺安一著
『お雇い外国人エドウィン・ダン―北海道農業と畜産の夜明け 』 』
参考書は↓ 国際結婚のコーナーで。 国際結婚のコーナーで。 |
ヘルハルト・ペルス・ライケン
Gerhard Christiaan Coenraad Pels Rijcken | (1810~1889)
オランダの海軍軍人。1855年にオランダ国王ウィレム三世から将軍家定に寄贈されたスンビン(スームビング)号艦長として来日。そのまま長崎海軍伝習所教授として日本に雇用された。主に航海術と運用術を担当し、勝海舟、榎本武揚らを教えた。スンビン号は「観光丸」と改名され、江戸へ巡航訓練を行うなど実習に使われた。ライケンは約2年間滞在した後カッテンディーケらの第2教育団と交代し帰国。母国では中将にまで進級し、海軍大臣を務めた。 | 星亮一著
『長崎海軍伝習所 (角川文庫) 』
』 |
ヴィレム・ホイセン・ファン・カッテンディーケ
(カッテンダイケ、カッテンデイケ、カッテンデーケ)
Willem Johan Cornelis ridder Huijssen van Kattendijke | (1816~1866)
オランダの海軍軍人、政治家。1857年、ペリーの黒船を見た徳川幕府はオランダに同様な軍艦を発注。カッテンディーケは、完成したJapan(ヤーパン)号の艦長として大西洋、インド洋をまわり1857年に長崎に入港した。そのまま幕府が開いた長崎海軍伝習所の教官となり、2年に渡って勝海舟、榎本武揚らなどの幕臣に精力的に航海術・砲術・測量術などの近代海軍の教育を行った。その間、長崎の自然・風景や人々の風習や行事や島津斉彬、鍋島閑叟らの人物像なども記録した書を残している。帰国後は1861年オランダ海軍大臣となり、一時は外務大臣も兼任した。因みに1860年、ヤーパン号はカッテンディーケの教え子である勝海舟船長をはじめとする遣米使節団一行が太平洋を横断してアメリカまで渡った船「咸臨丸」となった。 | 『長崎海軍伝習所の日々 (東洋文庫)
藤井哲博著
『長崎海軍伝習所―十九世紀東西文化の接点 (中公新書) 』
』 |
ヨハネス・ポンペ・ファン・メーデルフォールト
Lijdius Catharinus Pompe van Meerdervoort | (1829~1908)
幕末のオランダ人医師。長崎海軍伝習所のカッテンディーケに選任され、軍医を育てるための医学教授として弱冠28歳で1857年に日本で雇用された。ポンペは離日する1862年までの5年間に長崎に医学伝習所(長崎大学医学部の前身)を設立し松本良順、長与専斎などを育てる一方、養生所も設立し、計15,000人の診療を行った。これが「日本初の近代的な病院」と言われる。
| 『ポンペ化学書―日本最初の化学講義録 』
』 |
スネル兄弟(シュネル兄弟)
(兄John Henry Schnell、日本名:平松武兵衛、1843年?~?)
弟Edward Schnell、1844年?~?)
| 幕末から明治にかけて武器・兵器を売ったいわゆる「死の商人」として知られている兄弟だが、プロシア人ともオランダ人とも言われ、詳細は不明である。横浜で「バスケ・スネル商会」を設立、欧米からの物資を輸入販売する貿易商を営む。居住する外国人のために搾乳所を開設、これが日本で始めて牛乳を販売したと言われる。1867年にスイス総領事書記官となって翌年、新潟に移る。弟・エドワルドは「エドワルド・スネル商会」を設立する。同年、戊辰戦争が起こると奥羽越列藩同盟に近づいて武器・弾薬を送り込んだ。長岡藩の河井継之助にもガトリング砲を売り込んでいる。兄・ヘンリーは会津藩藩主松平容保に招かれて砲術指南となり、明治維新後の1869年には、戦いに敗れた会津若松の人々約40人と共に米カリフォルニア州に移住した。サンフランシスコの北東にあるゴールド・ヒルに「若松コロニー」という名の開拓地を建設した。この入植に参加していた17歳の少女「おけい」は、スネル邸で子守をしていた女性で、日本人女性で初めて海外に移民した人物として早乙女貢の小説『おけい』に詳しく描かれている。1871年4月、ヘンリーは経営が行き詰ったコロニーの金策のため、日本へと向かったとされるが、その後の消息は不明で、日本で秘密裏に暗殺されたとも言われる。弟は新潟から東京へ移り、そこで商会を開いた。彼もその後の経緯は不詳である。 | 高橋義夫著
『幕末怪商伝 (時代小説文庫) 』 』
早乙女貢著
『続 会津士魂〈6〉雄飛の巻 』 』
|
ロバート・ルイス・スティーブンソン
Robert Louis Balfour Stevenson | (1850~1894)
『宝島 』(1883)、『ジキル博士とハイド氏 』(1883)、『ジキル博士とハイド氏 』(1886)でよく知られるイギリスの作家。来日したことは無いが、知り合った日本人正木泰造(当時開成学校教授で後に東京職工学校=現・東工大の初代校長)から彼の師だった吉田松陰の事を聞かされて感銘を受け、1880年3月、英国の雑誌に『ヨシダ・トラジロウ』という伝記を発表した。これが世界で最初に書かれた松陰の伝記であり、彼は松陰の業績や思想を絶賛している。因みに彼の祖父ロバート・スチーブンソンは灯台技師でブラントンの師に当たる。 』(1886)でよく知られるイギリスの作家。来日したことは無いが、知り合った日本人正木泰造(当時開成学校教授で後に東京職工学校=現・東工大の初代校長)から彼の師だった吉田松陰の事を聞かされて感銘を受け、1880年3月、英国の雑誌に『ヨシダ・トラジロウ』という伝記を発表した。これが世界で最初に書かれた松陰の伝記であり、彼は松陰の業績や思想を絶賛している。因みに彼の祖父ロバート・スチーブンソンは灯台技師でブラントンの師に当たる。 | よしだみどり著
『日本より先に書かれた謎の吉田松陰伝 烈々たる日本人―イギリスの文豪スティーヴンスンがなぜ (ノン・ブック) 』
』
『物語る人(トゥシターラ)―『宝島』の作者R・L・スティーヴンスンの生涯 』
』
(著者のよしだみどりは元ロンパールームの先生!) |
モーティマー夫人
Mrs.Mortimer | (1802~1878)
19世紀に活躍した著名な児童文学作家。16冊の児童書を残すが、処女作『夜明けに』は38カ国で翻訳され、少なくとも100万部を売るベストセラーになった。日本に来たことはないが、想像で日本を描いた『不機嫌な世界地誌』の中に「邪悪な風習、ハラキリのある国」という章がある。
| トッド・プリュザン著
『モーティマー夫人の不機嫌な世界地誌-可笑しな可笑しな万国ガイド 』 』 |
ハーバート・G. ポンティング
Herbert George Ponting | (1870~1935)
イギリス生まれの写真家。1910年、スコット南極探検隊に参加し、写真と映像による記録を残す。南極に映画カメラを初めて持ち込んだ人物である。著書に“The Great White South”などがある。1902年ごろ、日露戦争のときに、アメリカの雑誌社の特派員として日本陸軍の第一師団に同行。1906年には再び日本を訪問。日本をことのほか愛し、「この世の楽園」と讃えた。京都の名工との交流、日本の美術工芸品への高い評価。美しい日本の風景や日本女性への愛情こもる叙述。浅間山噴火や決死の富士下山行など迫力満点の描写。江戸の面影が今なお色濃く残る百年前の明治の様子を多くの写真に残した。
| 『英国人写真家の見た明治日本―この世の楽園・日本 (講談社学術文庫) 』 』
『英国特派員の明治紀行 』 』 |
アリス・ベーコン
Alice Mabel Bacon | (1858~1918)
アメリカの女子教育者。日本の初めての女子留学生大山捨松、津田梅子の親友で、彼女らの要請で1884年、華族女学校(後の学習院女学校)英語教師として来日。来日中の1年間の手紙をまとめたものは1894年『日本の内側』として出版し反響を呼ぶ。帰国後はハンプトン師範学校校長となっていたが、1900年、大山と津田の再度の招聘により東京女子師範学校(後のお茶の水女子大学)と女子英学塾(後の津田塾大学)の英語教師として赴任、1902年4月に任期満了で帰国するまで明治期の女子教育に貢献した。彼女の著作は後にルース・ベネディクトの『菊と刀』の重要な参考資料になった。 | 『華族女学校教師の見た 明治日本の内側 』 』
『明治日本の女たち (大人の本棚) 』 』 |
クララ・ホイットニー
Clara A. N. Whitney Kaji | (1861~1936)
勝海舟の三男梶梅太郎の妻。1875年、15歳の時、商法講習所(一橋大学の前身)の教師として招かれた父親に従い来日。梅太郎と結婚し一男五女をもうけるが、後離婚、子供を連れて帰国した。日本にいた1875から1891年までの膨大な日記が残されているが、明治の要人らや風俗などが詳細に描かれている。 | 『勝海舟の嫁 クララの明治日記 (中公文庫) 』 』
参考書は↓ 国際結婚のコーナーで。 国際結婚のコーナーで。 |
チャールズ・ワーグマン
Charles Wirgman | (1832~1891)
1861年、イギリスの通信社の特派員として来日。幕末維新の歴史的な事件を取材し、その報道画を本国に送り、日本の情勢を伝えた。また、横浜居留地で日本最初の漫画雑誌『ジャパン・パンチ』(Japan Punch)を25年間にわたって刊行した。200冊をこえる冊数が発行されたといわれる。この雑誌に掲載された風刺漫画は「ポンチ絵」と呼ばれ、後の漫画文化に大きな影響を与えた。また雑誌に掲載された、スポーツ、ファッション、乗り物、音楽、美術など多岐に渡る文明開化の実像を伝え、幕末・明治維新時代の貴重な記録となっている。 | 『ワーグマン素描コレクション 』 』
ジョゼフ・ロガラ編・著
『Mr.パンチの天才的偉業―チャールズ・ワーグマンとジャパン・パンチが語る横浜外国人居留地の生活 1862‐1887 』 』 |
クラーク
William Smith Clark | (1826~1886)
「お雇い外国人」といえば日本人はまず彼を思い浮かべるのではないだろうか?化学・植物学を専門とする学者。マサチューセッツ州立農大学長だった時、新島襄、ケプロンの推薦と北海道開拓使の求めで来日、札幌農学校(後の北海道大学)の初代教頭に就任し創立時の学校運営と人材育成に尽力した。わずか9ヶ月間の滞在だったが、近代農業の講義のほかキリスト教精神による教育は、後に札幌農学校に学んだ内村鑑三・新渡戸稲造らに大きな影響を与えた。特に離日の際の
「青年よ大志を抱け Boys,be ambitious」
の言葉はあまりにも有名。
| 蝦名賢造著
『札幌農学校・北海道大学百二十五年―クラーク精神の継承と北大中興の祖・杉野目晴貞 』 』 |
エドワード・モース
Edward Sylvester Morse | (1838~1925)
アメリカの動物学・考古学者。小学校も卒業せず独学で生物学などを学び大学教授・博士になった。シャミセンガイを研究するため1877年来日、東大で生物学・動物学を講じ、ダーウィンの進化論などを紹介した。開通したばかりの汽車に乗り、横浜から新橋に向かう途中、車窓から貝殻のむき出しになった地層を偶然見つけ、さっそく発掘すると土器や石器が出土し日本の古代(縄文時代後期)の遺跡(大森貝塚)であることを発見。後の日本考古学・人類史研究の基礎を築いた。日本中を旅してまわり、日本人の生活の様子をスケッチし、生活用具や陶器を収集した。3万点に及ぶ民具はアメリカ・セイラムの博物館に収められている。その中には現在日本にも存在しない貴重な民具もある。
|
|
ハインリッヒ・エドムント・ナウマン
Heinrich Edmund Naumann | (1850~1927)
ドイツの地質学者。1875年明治政府の招きで来日し東大で地質学の初代教授となる。日本中の地質調査を実施し日本列島の成り立ちを明らかにした。本州の新潟から静岡・関東に至る巨大な地溝帯を発見しフォッサマグナと命名した。浜松・長野などで発見された古代のゾウは彼の名を取って「ナウマンゾウ」と名づけられた。
| 『日本地質の探究―ナウマン論文集 』
』
山下昇著
『フォッサマグナ 』 』 |
ジョン・ミルン
John Milne | (1850~1913)
イギリスの地震学者。ロンドン大学キングス・カレッジなどで地質学を学ぶ。1876年日本政府工部省の顧問として招かれ、工部省工学寮(後の工部大学校)で鉱山学・地質学を教えた。1880年、横浜で大地震に遭遇して以来、自ら開発した地震計を使って地震の研究を進め日本地震学会を創設、多くの論文を発表した。因みにこれが「世界初の地震学会」。イギリスではほとんど地震が無いのでミルンはよっぽどビックリしたに違いない。また石器時代の遺跡の発掘やアイヌ研究でも大きな成果を挙げている。日本人トネと結婚し1895年に帰国してからは、イギリス南部のワイト島(ジミヘンの晩年のコンサートでも有名ですな)に水平振子地震計を備えた地震観測所を作り、世界地震観測網の構築に努めた。トンボの一種「ミルンヤンマ」は彼の名に因んで付けられた。 | 『ジョン・ミルン博士の生涯』
『ミルンの日本人種論―アイヌとコロポクグル 』 』
森本貞子著
『女の海溝―トネ・ミルンの青春 』 』 |
ヘンリー・フォールズ
Henry Faulds | (1843~1930)
英スコットランドの宣教師・医師。1868年グラスゴー大学を卒業、アンダーソンカレッジで医学を学び医師となった。1871年長老派スコットランド教会の医療宣教師としてインドに渡り、その後1873年医療伝道団の一員として来日。当時外国人の居留地だった築地に居を構え、築地病院(後の聖路加病院:日野原先生で有名)を建て、布教と外科・眼科診療に当たった。また、目の不自由な人のための支援や医学を学ぶ学生を指導するなど1886年に帰国するまで12年もの間、幅広い活動をした。フォールズは、日本人が本人の証明のために証文などに拇印を押す習慣に興味を示し、またモース博士の大森貝塚発掘の手伝いをした時に出土した縄文土器の表面に付いていた「指紋」から「土器の作者を特定出来るのでは?」と指紋の研究を始めた。数千の指紋を集め、指紋は個人によってすべて異なること、除去しても再生すること、成長しても変わらないことなどを確認、1880年10月、英国の科学雑誌「ネイチャー」に日本から科学的指紋法に関する論文を投稿、指紋による犯罪者の個人識別の可能性を発表した。フォールズは帰国後にさらに本格的な研究を始め、弓状紋・蹄状紋・渦状紋など5つの基本パターンに分類し、また指紋の遺伝関係なども確認した。しかし彼の研究は、当初、指紋による犯罪者特定を否定しようとする上流階級の権威ある科学者ゴールトン(ダーウィンの従兄弟)の画策などによって無視されてしまった。ようやく1901年になってロンドン警視庁が「ヘンリー式指紋法」を全面的採用し、科学的犯罪捜査は飛躍的な進歩を遂げた。これは後に世界中に普及し、現在でもなお「個人の特定」「犯罪捜査」の基本であり有効な手段となっている。彼の日本での居住地跡には警視庁が建てた「指紋研究発祥の地 ヘンリー・フォールズ住居跡」の記念碑がある。
| コリン・ビーヴァン 著
『指紋を発見した男―ヘンリー・フォールズと犯罪科学捜査の夜明け 』 』
|
レオポルド・ミュルレル
Benjamin Carl Leopold Muller | (1824~1893)
ドイツの医師。陸軍軍医少佐だった1871年、明治政府の招聘により、ドイツ式の医学を移入するためテオドール・ホフマンとともに来日。東校、第一大学区医学校、東京医学校で外科、眼科、婦人科を教授。3年の任期を終えて1875年に帰国。
| 幕末から廃藩置県までの西洋医学
|
テオドール・ホフマン
Theodor Eduard Hoffmann | (1837~1894)
ドイツの内科医・医学者。海軍軍医少尉だったが1871年東京医学校(後の東大医学部)の招きで来日。日本の医療・医学をドイツ式のものにすべく改革を進めた。内科学・栄養学を主に講義し日本に初めて「栄養」についての知識をもたらせ、脚気・寄生虫病などの対処法も講じた。また初めて穿胸術や肋骨切除術も伝えた。1875年の帰国まで日本人の人類学的特徴などを研究した。
| (調査中) |
ウイリアム・ウィリス
WIlliam Willis | (1837~1894)
イギリス(北アイルランド)の医師。1862年イギリス公使館の医員として来日、約15年に渡って駐在し日本の医学の発展に大きく寄与した。来日直後に発生した生麦事件の被害者の治療や戊辰戦争に従軍し兵士たちの治療に当たる。鳥羽・伏見の戦の時は重傷を負った西郷隆盛の弟、西郷従道の治療に当った。その後は東大で教鞭に立ち、日本の臨床医学の発展と東大病院の創立に尽力した。後に西郷の縁で鹿児島医学校兼病院に移り治療と更新の育成に努めた。アーネスト・サトウとは親友。
| (調査中) |
ゴットフリード・ワグネル
Gottfried Wagener | (1831~1892)
ドイツの実業家。21歳の若さで数学物理学の博士号を取得、パリやスイスで工業学校などで教師をしていた。極東で事業展開していた米企業ラッセル商会の石鹸工場設立のため1868年に長崎に招聘されたがまもなく佐賀藩に雇われて有田焼の近代化に助力した。1870年には上京し大学南校・東校(現・東大)に雇われてドイツ語・数学・博物学・物理学・化学などを講じた。東京職工学校(現東工大)、京都の医学校(現・京都府立医科大学)などでも教え、多くの教え子を育てた。七宝焼の研究や旭焼の創設をはじめ生涯をガラス製品・陶器の大量製造・品質向上、欧米への紹介に努めた。
| 永竹威著
『日本のやきもの〈4〉有田・九谷 (講談社カルチャーブックス) 』
』 |
ベルツ
Erwin von Balz | (1849~1913)
ドイツ出身の内科医。お雇い外国人のうち、日本で一番知られた医学者だろう。1875年、東京医学校(現・東大医学部)の教師として来日。29年に渡って日本に滞在し、多くの優秀な門下生を育て日本医学の発展に尽くした。また、日本人の身体的特徴の研究や脚気、寄生虫病などの治療・予防に当たった。明治天皇、皇太子(後の大正天皇)の主治医であり、伊藤博文は親友であった。また、ベルツが残した日記などには、明治時代の日本が行った西洋文明輸入に際しての姿勢に対しての的確な批判や警告が多く含まれている。一方で失われていく日本の文化・伝統を守るため多くの日本画、美術品、伝統工芸品や民具などを蒐集し保存に努めた。それらのほとんどが母国ドイツのシュトゥットガルトのリンデン民族学博物館に収められている。学校での検便、臨海学校、「温泉は体にいい」ことなどを日本に普及させ、草津温泉を「世界最高の湯治場」として「再開発」したことでも有名。
| 『ベルツの日記〈上〉 (岩波文庫) 』
』
ゲルハルト・ヴェスコヴィ著
『エルヴィン・ベルツ―日本医学の開拓者 』
』
真寿美・シュミット・村木著
『「花・ベルツ」への旅 』
』
参考書は↓
国際結婚のコーナーで。 |
ヨンケル・フォン・ランゲッグ
Ferdinand Adalbert(Ethelbert)Junker von Langegg | (1828~1901)
ロンドンで「ユンカーの麻酔器」を発明するなど功績を挙げたドイツ出身の眼科の臨床医・医療器具の発明家。1872年、京都府療病院(現・京都府立医科大学)の創設にあたり府が初代教師として独の名門ライプツィヒ大学より招いた。1876年に帰国するまで解剖学や麻酔の講義を行い、日本の近代麻酔術などを育て上げる一方、日本の説話・伝説民話を収集、帰国後『瑞穂草』『扶桑茶話』としてライプツィヒで出版した。
| 外国人のみたお伽ばなし―京のお雇い医師ヨンケルの『扶桑茶話』 |
オスカル・ケルネル
Oskar Kellner | (1851~1911)
ドイツの実業家・農芸化学者。駒場農学校(後の東大農学部)で近代農業(特に土壌肥料学)の実践と発展に尽力した。東京目黒区の駒場野公園には「ケルネル田圃」という実習用田んぼが残されている。
| (調査中) |
メルメ・カション
Mermet Cachon | (1828~1870)
フランスの宣教師・医師。1859年琉球を経て函館に来日、教会に併設した病院で布教と治療に従事した。その傍らアイヌの研究をしアイヌ語辞典を著した。1864年ロッシュの助手として再来日し通訳などを務めた。
| 富田仁著
『メルメ・カション―幕末フランス怪僧伝 (1980年) (有隣新書) 』 』 |
アストン
William George Aston | (1841~1911)
北アイルランド出身。1863年イギリス公使館員として来日。1875年から約5年間神戸領事として駐留。また、岩倉使節団がイギリスを訪問した時は通訳を務めている。傍ら日本の研究も進め、日本語文法書や日本の古典を紹介した『日本紀』(1896)などを出版した。サトウ、チェンバレンとともに三大ジャパノロジスト(日本研究家)と呼ばれている。
| 楠家敏著
『W.G.アストン―日本と朝鮮を結ぶ学者外交官 (東西交流叢書) 』 』 |
パーシヴァル・ローウェル(ローエル)
Percival Lowell | (1855~1916)
アメリカ出身の日本の研究家であり世界的な天文学者。ハーバード大学で物理や数学を学び、後実業家となった。1883年来日し日本の研究を始め、その後3度再来日した。石川県能登などや日本を代表する山、その信仰をテーマに『極東の魂』など4冊を著した。この『極東の魂』の本を読んでハーン(小泉八雲)は来日を決めたといわれる。帰国後は本格的に天文学者となり冥王星の存在を「予知」した。
| 『極東の魂 (公論選書 8) 』 』
『NOTO―能登・人に知られぬ日本の辺境 』 』
宮崎正明著
『知られざるジャパノロジスト―ローエルの生涯 (丸善ライブラリー) 』 』 |
チェンバレン
Basil Hall Chamberlain | (1850~1935)
イギリスの言語学者。俳句を英訳した最初の人物の一人であり、日本についての事典"Things Japanese"や『口語日本語ハンドブック』などといった著作で知られ、19世紀後半~20世紀初頭の最も有名な日本研究家の一人。1873年23歳で来日、海軍兵学寮(後の海軍兵学校)で英語を教え、1886年からは東京帝国大学教授となり、39年に渡り日本に滞在し金田一京助ら日本の言語学者らを育てながら自身で研究を重ねた。『古事記』の英訳、アイヌ・琉球の研究、日本語文法などに関する書を多く著している。王堂、チャンブレンとも自称し和歌なども残している。
小泉八雲はチェンバレンの薫陶を受け、二人は交遊があり往復書簡が残されているが後に日本に対する姿勢の違いから次第に疎遠になっていった。その辺の事情は平川祐弘著『破られた友情―ハーンとチェンバレンの日本理解 』に詳しい。 』に詳しい。
| 『日本事物誌 (1) (東洋文庫) 』
』
楠家重敏著
『イギリス人ジャパノロジストの肖像―サトウ、アストン、チェンバレン 』
』 |
ルーサー・メーソン
Luther Whiting Mason | (1818~1896)
アメリカの教育者。日本の音楽教育・西洋式音楽の輸入などの基礎を築いた功労者。アメリカ各地で長年音楽の教師を勤め、主に初等音楽教育の第一人者であった。アメリカに留学していた文部省の伊沢修二に唱歌の指導をしたのが縁となり、1880年に明治政府に招聘され2年間の契約で日本に渡った。メーソンは、音楽取調掛(後の東京音楽学校=東京芸大音楽学部)の担当官となった伊沢とともに、音楽教員の育成方法や教育プログラムの開発を行い、『小学唱歌集』にも関わった。また、ピアノとバイエルの『ピアノ奏法入門書』を持ち込み、ピアノ演奏教育の基本も築いた。芸大にはメーソンがアメリカから持ち込んだピアノが今も記念に残されている。 | 上沼八郎著
『伊沢修二 (人物叢書) 』
』 |
イザベラ・バード
Isabella Lucy Bird | (1831~1904)
イギリスの女流作家。当時の女性としては珍しい「旅行家」として、世界中を旅した。1878年、47歳で来日し東京を起点に日光から新潟へ抜け、日本海側から北海道に至る北日本を旅した(ヘボン博士の紹介で「伊藤」という従者兼通訳の日本人男性一人のみが同伴した)。後に京都や伊勢神宮などを巡る関西地方も旅行し、これらの記録を『日本奥地紀行』『バード 日本紀行』(Unbeaten Tracks in Japan)として残した。特にアイヌの生活ぶりや風俗については、まだアイヌ文化の研究が本格化する前の明治時代初期の状況をつまびらかに紹介したほぼ唯一の文献で貴重。以下は日本について語った有名な一文。
「私はそれから奥地や蝦夷を1200マイルに渡って旅をしたが、まったく安全でしかも心配もなかった。世界中で日本ほど婦人が危険にも無作法な目にもあわず、まったく安全に旅行できる国はないと信じている」 | 『日本奥地紀行 (平凡社ライブラリー) 』 』
『イザベラ・バードの日本紀行 (講談社学術文庫 1871) 』 』
多和田葉子著
『球形時間 』(時空を超えてイザベラ・バードが登場するSF!)
』(時空を超えてイザベラ・バードが登場するSF!) |
ヴェンセスラウ・デ・モラエス
Wenceslau Jose de Sousa de Moraes | (1874~1929)
ポルトガル人外交官(海軍軍人)・文筆家。日本の風情・人情・自然に魅せられ、没するまで約30年間日本に暮らした。マカオなどで海軍の高官として勤務した後、1889年初来日。日本に初めてポルトガル領事館が開設されると在神戸副領事として赴任、のち総領事となり、1913年まで勤める。神戸で芸者ヨネと知り合い結婚。しかしヨネが死んだため総領事を辞してヨネの故郷徳島に移り住んだ。その後ヨネの姪小春と暮らすが小春にも先立たれ、その後は徳島で一人暮らしし、孤独の中で著作と墓参の日々を過ごした。1929年自宅の土間で死んでいるのを発見され地元住民らによって葬式が営まれた。『おヨネとコハル 』『大日本』『日本精神 』『大日本』『日本精神 』『徳島の盆踊り―モラエスの日本随想記 』『徳島の盆踊り―モラエスの日本随想記 』や日本についての著作があり、また日記・書簡など、ポルトガルの新聞や雑誌などに寄稿した文章が多数残されているが、ポルトガル語であるため、日本ではあまり知られることがなかった。著作のほとんどが彼の死後、日本語に訳されて日本礼讃の書として知られるようになった。 』や日本についての著作があり、また日記・書簡など、ポルトガルの新聞や雑誌などに寄稿した文章が多数残されているが、ポルトガル語であるため、日本ではあまり知られることがなかった。著作のほとんどが彼の死後、日本語に訳されて日本礼讃の書として知られるようになった。
参考書は→ 国際結婚のコーナーで。 国際結婚のコーナーで。 | 新田次郎著
|
ウィリアム・ゴーランド(ガウランド)
William Gowland | (1842~1922)
イギリス生まれ。大阪造幣寮(造幣局)の技師として1872年に来日した化学兼冶金技師。16年間在任し、その間反射炉の築造や日本人技師の育成などを行い産業の発展に大きく寄与する一方、日本の古墳研究の先駆者としても活躍、「日本考古学の父」と呼ばれている。さらに、趣味として1874年(明治7年)に、アトキンソン(東京開成学校教授・日本酒の研究で有名)、サトウとの外国人3人で、ピッケルなどを用いた近代登山を日本で初めて神戸の六甲山で行った。また、地形がヨーロッパのアルプスに似ていることから長野・岐阜~山梨・静岡にまたがる大山脈を「日本アルプス」と名づけた。1881年にチェンバレンが編集した『日本についてのハンドブック』の中で、「日本アルプス(Japanese Alps)」として紹介され知られるようになった。本国でもストーンヘンジの研究などで知られている。 | ヴィクター・ハリス著
『ガウランド日本考古学の父 』
』 |
ウォルター・ウェストン
Walter Weston | (1861~1940)
イギリス生まれ。1889年宣教師として来日。趣味として日本の本州の大山脈を踏破、日本人未踏の山も数々登頂。1896年『日本アルプスの登山と探検』をイギリスで出版。ゴーランドが命名した「日本アルプス」の名を内外に広めた。その後も何度か日本を訪れ、日本人に近代の登山方法を指導した。 | 『日本アルプス―登山と探検 (平凡社ライブラリー) 』 』
田畑真一著
『知られざるW・ウェストン 』 』 |
テオドール・フォン・レルヒ
Theodor von Lerch | (1869~1945)
オーストリアの軍人(当時・少佐)。悪名高い八甲田山での遭難事件を教訓に寒冷地での軍事教練を強化・指導するために招聘された。1911年、新潟県高田(現上越市)で初めて日本人にスキーを伝えた。その時はまだスポーツとしてではなくあくまでも雪中を早く移動する手段であり、ストックは一本づえであった。上越市では少佐の業績を記念して毎年2月に「レルヒ祭」が行われる。 | 長岡忠一著
『スキーの原点を探る―レルヒに始まるスキー歴史紀行 』 』 |
ピエル・ロチ
(ピエール・ロティ)
Pierre Loti | (1850~1923)
南フランス・ロッシュフォール出身。本名ルイ・マリー=ジュリアン・ヴィオー。本業は海軍大佐で世界中を旅し、『氷島の漁夫 (岩波文庫) 』など多くの著作で世界的にも有名な作家だった。1885年、修理のため長崎に停泊した巡洋艦ラ・トリオンファント号の乗員として来日。中国に立つまで約2ヶ月の間長崎に滞在し、周旋人を通して17歳のおかねという少女と月20ピアストル(約40円)で愛人関係を結び、十人町の家を借りて1ヵ月ほど共に暮らした。その経験を後に『お菊さん Madame Chrysantheme』という小説に書き、フィガロ紙に1887年に発表した。日本の自然や生活様式などを異国情緒たっぷりにリアルに描いたこの作品は、また従順で大人しい日本女性のイメージが強く印象づけられている。これは多くの欧米人を刺激し、フランスのジャポニズムにも大きな影響を与えた。アメリカのジョン・ルーサー・ロングはこの日本人女性の話を長崎にいた姉から聞き、短編小説にした。これらがプッチーニのオペラ『蝶々夫人』の原型になった。大津事件で殺されかけたロシアの皇太子はこの『お菊さん』の愛読者だった。それにしてもロチの描く日本人女性の姿はひどく、意思も感情も表情もない。また日本を「遅れた野蛮な国」のように描写している。1900年には2回目の来日を果たし、後日談として『お梅さんの三度目の春』という小説を書いた。長崎公園にはロチの碑がある。 』など多くの著作で世界的にも有名な作家だった。1885年、修理のため長崎に停泊した巡洋艦ラ・トリオンファント号の乗員として来日。中国に立つまで約2ヶ月の間長崎に滞在し、周旋人を通して17歳のおかねという少女と月20ピアストル(約40円)で愛人関係を結び、十人町の家を借りて1ヵ月ほど共に暮らした。その経験を後に『お菊さん Madame Chrysantheme』という小説に書き、フィガロ紙に1887年に発表した。日本の自然や生活様式などを異国情緒たっぷりにリアルに描いたこの作品は、また従順で大人しい日本女性のイメージが強く印象づけられている。これは多くの欧米人を刺激し、フランスのジャポニズムにも大きな影響を与えた。アメリカのジョン・ルーサー・ロングはこの日本人女性の話を長崎にいた姉から聞き、短編小説にした。これらがプッチーニのオペラ『蝶々夫人』の原型になった。大津事件で殺されかけたロシアの皇太子はこの『お菊さん』の愛読者だった。それにしてもロチの描く日本人女性の姿はひどく、意思も感情も表情もない。また日本を「遅れた野蛮な国」のように描写している。1900年には2回目の来日を果たし、後日談として『お梅さんの三度目の春』という小説を書いた。長崎公園にはロチの碑がある。 | 『お菊さん (岩波文庫) 』 』
『秋の日本 (角川文庫) 』 』
『ロチのニッポン日記―お菊さんとの奇妙な生活 (有隣新書 12) 』 』
『お梅が三度目の春 (1952年) 』 』
岡谷公二著
ピエル・ロティの館―エグゾティスムという病い (叢書メラヴィリア)
落合孝幸著
ピエール・ロティ―人と作品 |
カール・ブッセ
Carl Hermann Busse | (1872~1918)
ドイツ出身の新ロマン派の詩人。1905年、上田敏の訳詩集『海潮音』に収められた詩『山のあなた(Uber den Bergen)』でよく知られている(三遊亭歌奴=現:圓歌の落語「授業中」で僕らは親しんでいるが)。その全文は以下
山のあなたの空遠く
「幸(さいはひ)」住むと人のいふ。
噫(ああ)、われひとと尋(と)めゆきて、
涙さしぐみ、かへりきぬ。
山のあなたになほ遠く
「幸」住むと人のいふ。
だが、それ以前の1887年、来日して東大で5年に渡り哲学を講じていた!。ブッセはドイツに帰国後に大学教授となり、1892年出版した『詩集』で認められ、以後『新詩集』『放浪者』などの詩集を発表、小説や評論、ヘルマン・ヘッセら新人を発掘した。つまり来日後に世界的な名声を得た人である。因みに上田敏は東大大学院で小泉八雲に師事していた。ブッセと面識は無い。
| 海潮音―上田敏訳詩集 (新潮文庫) |
|